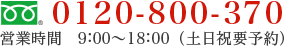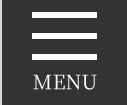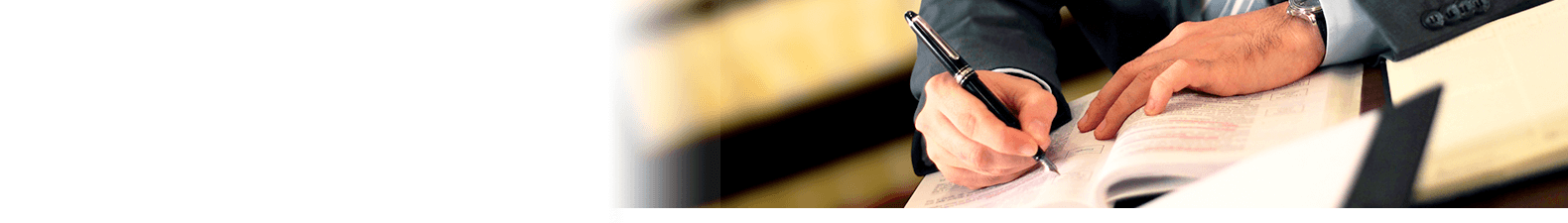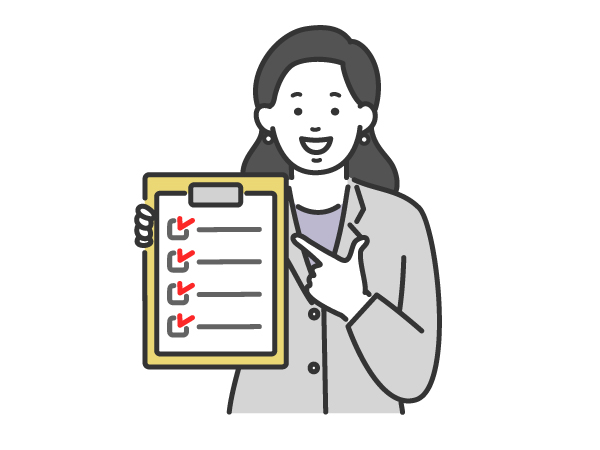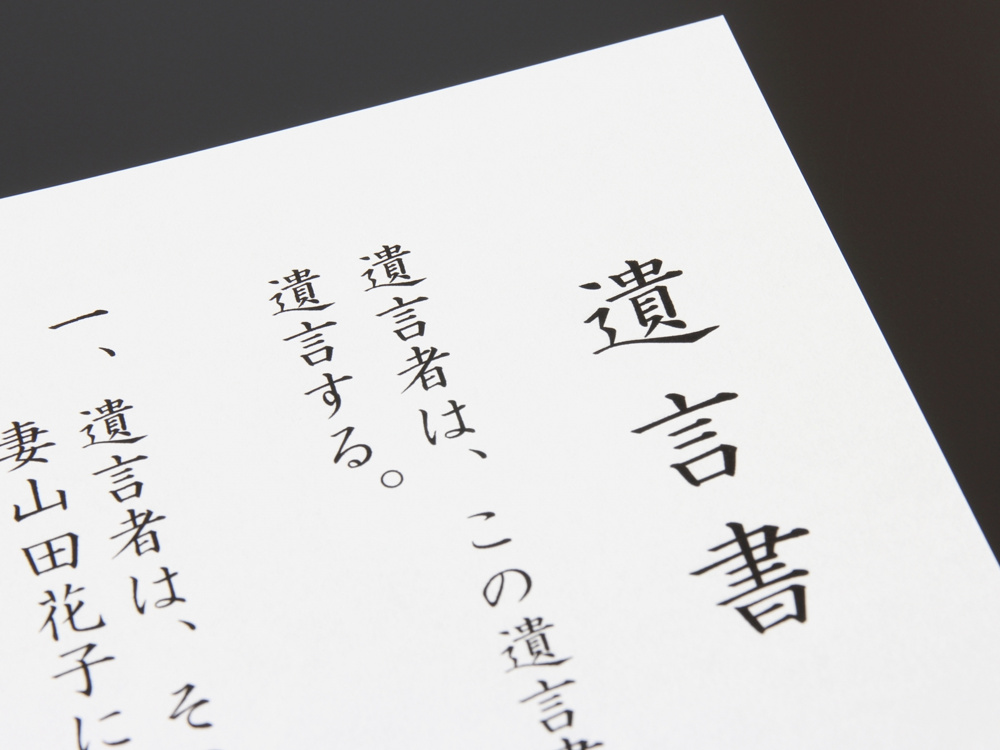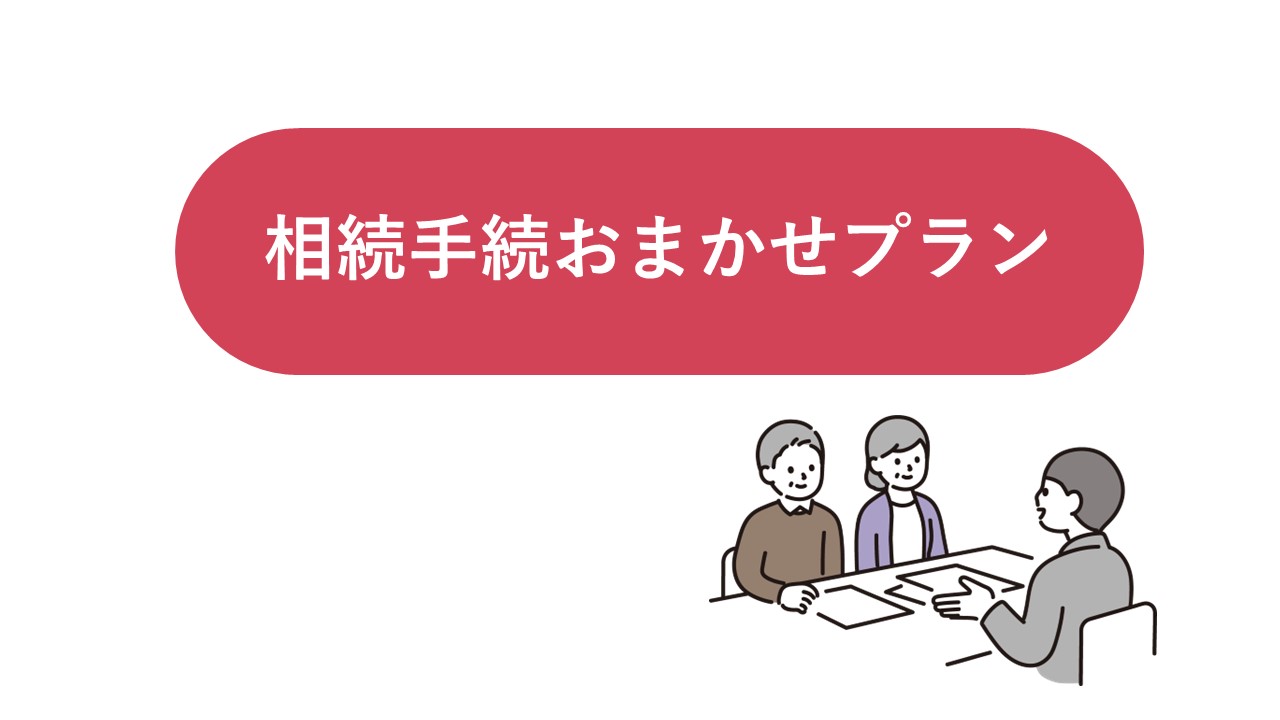こんにちは。リーガル・フェイスです。
当士業コラムでは、いつもは個人の方の相続手続きや生前対策をテーマにしていますが、今回は会社(事業)の引継ぎについてお話しさせていただきます。
昨今、中小企業の後継者不足が深刻な社会問題となっています。
日本国内の企業の99%を占めている中小企業が、雇用創出や技術革新などにおいて重要な役割を果たしていることは言うまでもありません。
後継者の不在による廃業の増加の結果、雇用や地域経済に重大な影響をもたらすことが懸念されています。
そこで知ってきたいのが「事業承継」です。
そもそも企業の事業承継とはどのようなものなのか?
何か対策すべきことはあるのか?
1.事業承継とは
事業承継とは、会社や事業を次の後継者に引き継ぐことをいいます。
長年にわたり培ってきた技術や貴重なノウハウ、従業員を引き継ぐことが可能となる重要なプロセスです。
事業承継で引き継ぐものとして、主に経営権・資産・経営理念などが挙げられます。
具体的には、後継者となる人物、経営権、事業用資産や資金、そして経営理念やノウハウ、ブランド、顧客情報などの目に見えない経営資源がこれに含まれます。
| 人(経営)の承継 |
要素:経営権、経営者としての資質、経験、人脈など 内容:代表権や株式の承継、後継者としての経営能力や資質、事業を円滑に進めるための人脈や情報を引き継ぐ |
| 資産の承継 |
要素:株式、事業用資産(不動産、設備など)、資金、事業用借入金など 内容:会社の所有権を示す株式や、事業の運営に不可欠な不動 |
| 知的資産の承継 |
要素:経営理念、経営ノウハウ、ブランド、特許、顧客情報、信用、独自の技術など 内容:企業独自の強みや価値となるような、目に見えない経営資源を引き継ぐ |
2.事業承継を行う3つの方法
事業承継は、引き継ぐ先によって3つの種類があります。
① 親族への承継
経営者の子供や親族が後継者となる方法
特長:経営理念や価値観の共有が容易で、従業員の理解も得やすい傾向があります。
また、早いうちから後継者育成に取り組むことができます。
② 従業員への承継
親族以外の従業員や役員などが後継者となる方法
特長:親族内承継に比べて、後継者の選択肢が広がります。
経営能力のある人材を見極めて承継することができ、経営方針の一貫性が期待できる反面、M&Aに比べて事業の成長が見込めない場合もあります。
③ M&A(社外への承継)
社外の第三社企業や創業希望者に対して事業承継を行う方法
特長:親族や従業員に候補者がいない場合でも外部から広く候補者を募りやすく、また現経営者は会社売却による利益が見込める場合もあります。
3.事業承継の流れ
次に、一般的な事業承継の流れを段階的に確認してみましょう。
① 準備(現状分析)
①-1 会社の現状把握
自社の財務状況や経営状況、強み、弱み、資産、債務などを分析します。
後継者を選定するための基盤となります。
①-2 後継者の選定
親族、従業員、またはM&Aによる第三者から、後継者候補を選定します。
①-3 事業承継計画の策定
後継者の育成計画や、後継者選定後の具体的な承継計画(いつ誰に何を引き継ぐのか)を策定します。
必要に応じて、自社株の対策や経営改善も計画に含めます。
② 後継者の育成
後継者が円滑に経営を引き継げるよう、経営に関する知識や経験を積ませます。
経営改善の取り組みも並行して行います。
③ 事業承継の実行
事業承継を実際に行う段階です。
株式の譲渡、役員(経営陣)の交代、事業資産の移転などを、後継者や関係者間の合意に基づいて実行します。
事業承継の方法(親族内承継・従業員承継・M&A)によって手続きは異なります。
4.事業承継の対策と注意点
① 生前実現型の対策
現経営者が存命中に後継者へ経営権を移譲し、現経営者が死亡しても後継者の経営権に支障が生じないようにする対策を「生前実現型」といいます。
以下に「生前実現型」対策の例を挙げてみます。
■事業用資産の売買
現経営者が、生前、後継者に対し株式等の事業資産を売買する方法です。この方法では、売買した時点で後継者が株式を取得し、経営権を早期に移譲することができます。
株式の売買価格が適正であれば、相続発生時の遺留分侵害額請求(※)の対象ともならず、株式の分散を防止することができます。
■事業用資産の贈与
現経営者が、生前、後継者に対し株式等の事業資産を贈与する方法です。この方法でも、売買と同じく、贈与した時点で後継者が株式を取得し、経営権を早期に移譲することができます。また、後継者が株式の買取資金を有している必要もありません。
一方で、贈与税や相続発生時の持ち戻し(※)、遺留分侵害額請求に注意が必要です。
「持ち戻し(もちもどし)」とは、相続人間の公平を保つために、生前に被相続人から特別の利益(特別受益)を受けたとみなされる相続財産を、相続財産に加えて再計算する制度。
本ケースの場合、現経営者から後継者への株式贈与が特別受益となり、相続財産や相続税に影響を与える可能性がある。
② 生前準備型の対策
現経営者が存命中に経営権を移譲する準備だけしておき、実際に経営権が移譲されるのは経営者が死亡したタイミングとする対策を「生前準備型」といいます。
現経営者が亡くなるまでその経営権を維持でき、また「生前実現型」で発生しうる贈与税等の支出を回避する理由で、多くのケースで採用されている方法です。
■遺言、死因贈与契約の活用
現経営者が遺言や死因贈与契約を作成し、どの財産を誰に承継するかを明確にすることにより、後継者に株式や事業用資産を集中させることができます。
一方で、この場合、株式等の移転の効力が生じるのは相続発生時となるので、後継者への経営権の委譲がスムーズにいかない恐れがあります。
■種類株式の活用
種類株式とは、配当や議決権などに関して普通株式と異なる権利内容が定められた株式のことです。遺言や家族信託と併用することにより、有用な事業承継の対策となり得ます。
例えば、株主総会での議決権を持つ普通株式を後継者に、議決権を持たない種類株式を他の相続人に承継させる旨の遺言を作成しておくことで、複数いる相続人へ株式を分散させつつも、重要な経営判断の権限は後継者に集約し、円滑な事業承継と後継者の地位安定を図ることができます。
③ 株式を分散させない為の対策
特に対策をしないまま経営者が死亡した際、経営者の株式等の遺産はその相続人が遺産分割協議等の方法により取得する事となります。
後継者以外の相続人との関係性や、株式以外の遺産内容によっては、後継者がじゅうぶんな株式数を取得できない事も考えられますが、その際は以下の方法を検討してみましょう。
■買取資金等の調達
事業(会社)の後継者が株式等の事業用資産を相続する場合、他の相続人に対して代償金の支払いをせざるを得ないケースが考えられます。
後継者にその資金が不足している場合、借入による資金調達が必要となりますが、その際に「経営承継円滑化法」で設けられている金融支援を活用する方法があります。
これは、後継者が自社株式や事業用資産を買い取る等の資金調達を行う際の支援として、日本政策金融公庫や信用保証協会による融資や保証が低金利で利用しやすくなるというものです。
■相続人に対する売渡請求
会社は、定款で定めることにより、相続等で自社株を取得した者に対して、自社株を会社に売り渡すことを請求できます。
後継者以外の相続人から自社株を取得することにより、後継者の経営基盤の安定化を図ることができます。
【定款記載例】
第●条(相続人等に対する株式の売渡請求)
会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を会社に売り渡すことを請求することができる。
※注意点
請求期限:相続が発生したことを知ってから1年以内に、株主総会の特別決議を経て請求する必要あり
売買価格:売買価格は当事者間の協議によるが、調わない場合は裁判所に申立てる必要あり
■特別支配株主による株式等売渡請求
議決権の90%以上を有する後継者(=特別支配株主)は、他の株主全員に対して、その株式全部を自分に売り渡すことを請求することができます。
5.さいごに
今回は事業承継について調べてみました。
かなり複雑な内容ですが、中小企業の経営者の方においては避けて通れない分野ではないでしょうか。
本コラムは事業承継の手続きや対策の一端を記載したに過ぎませんが、将来のことを検討する一助となりましたら幸いです。
また、事業承継の実現や対策にあたっては、様々な書類の作成が必要となります。
リーガル・フェイスでは、株式譲渡契約書や株主総会議事録、遺言書、遺産分割協議書などの書類の作成代行や、役員変更などの会社登記の申請手続きも行なっております。
初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
(無料相談受付フリーダイヤル 0120-800-370)

大学(法学部)を卒業後、リーガル・フェイスへ入所。そこから14年間、補助者として不動産売買に伴う登記をメインとして業務に邁進し、2021年より相続・商業課へ異動。ただ「こなす」のではなく、自分だけの「付加価値」を付けながら一人ひとりのお客様へ最善のサービスを提供できるよう、新たな環境で日々勉強中。趣味はランニング、好きな食べ物は唐揚げと夏野菜(ナス、トマト、オクラなど)。