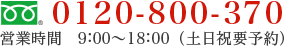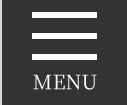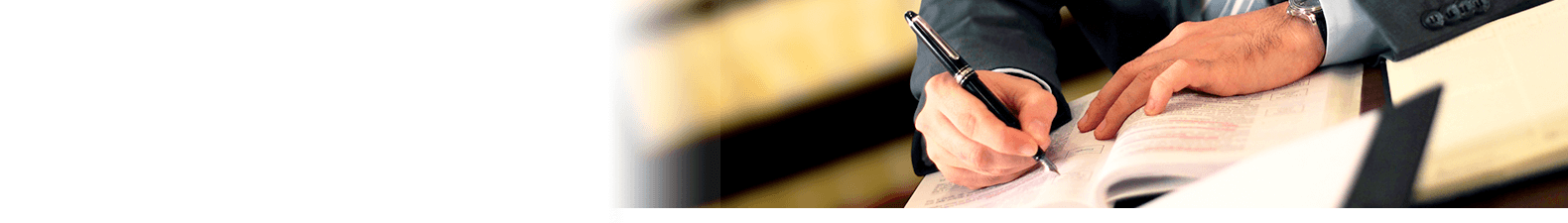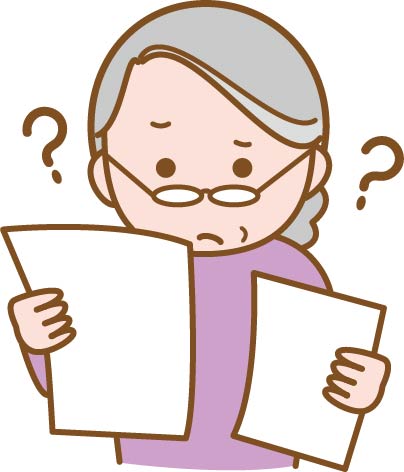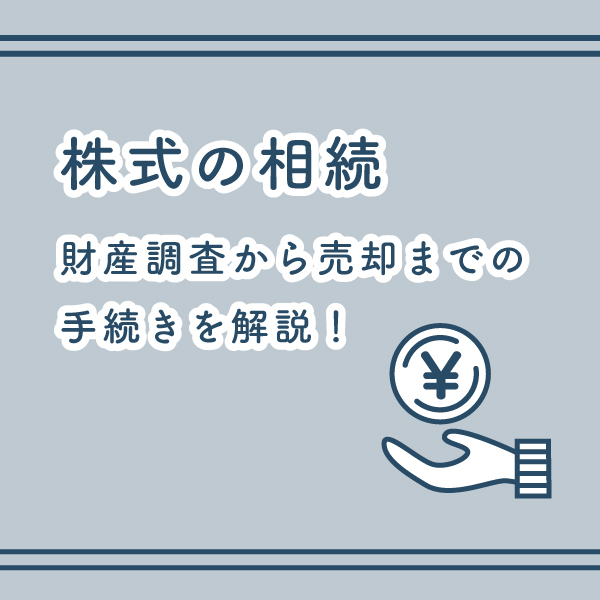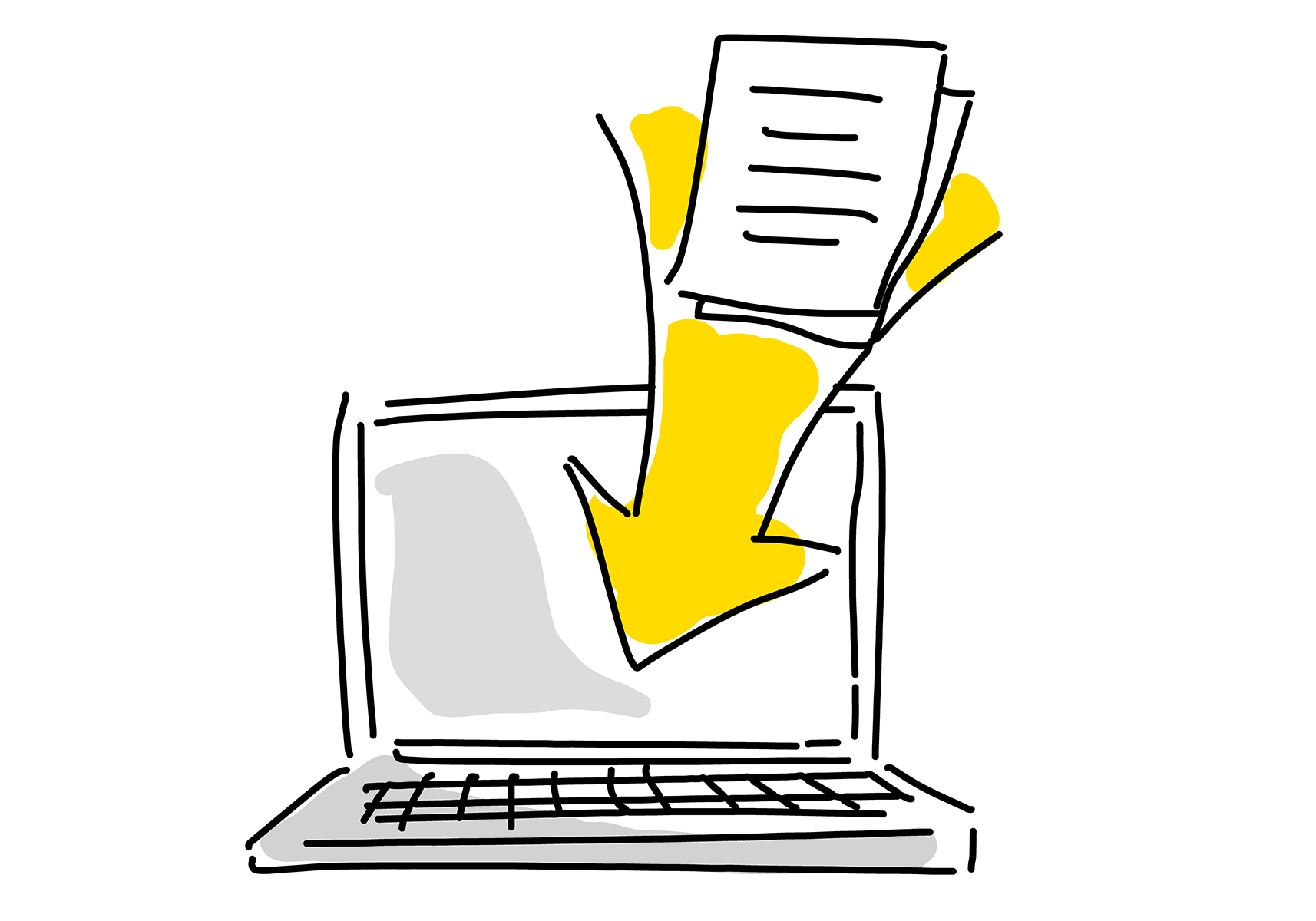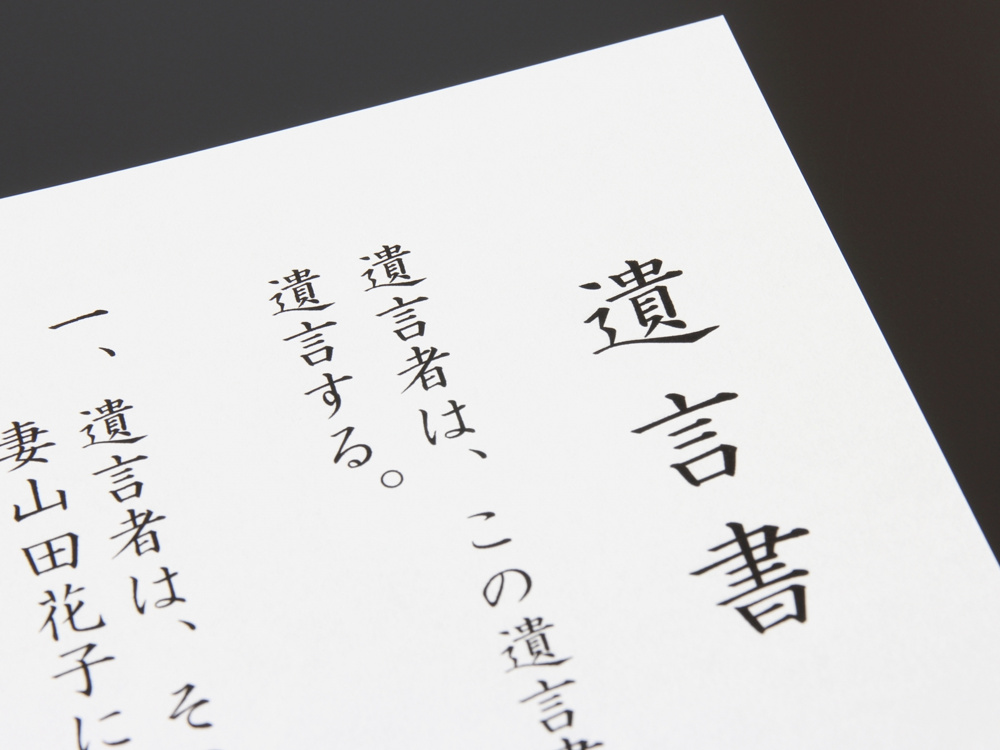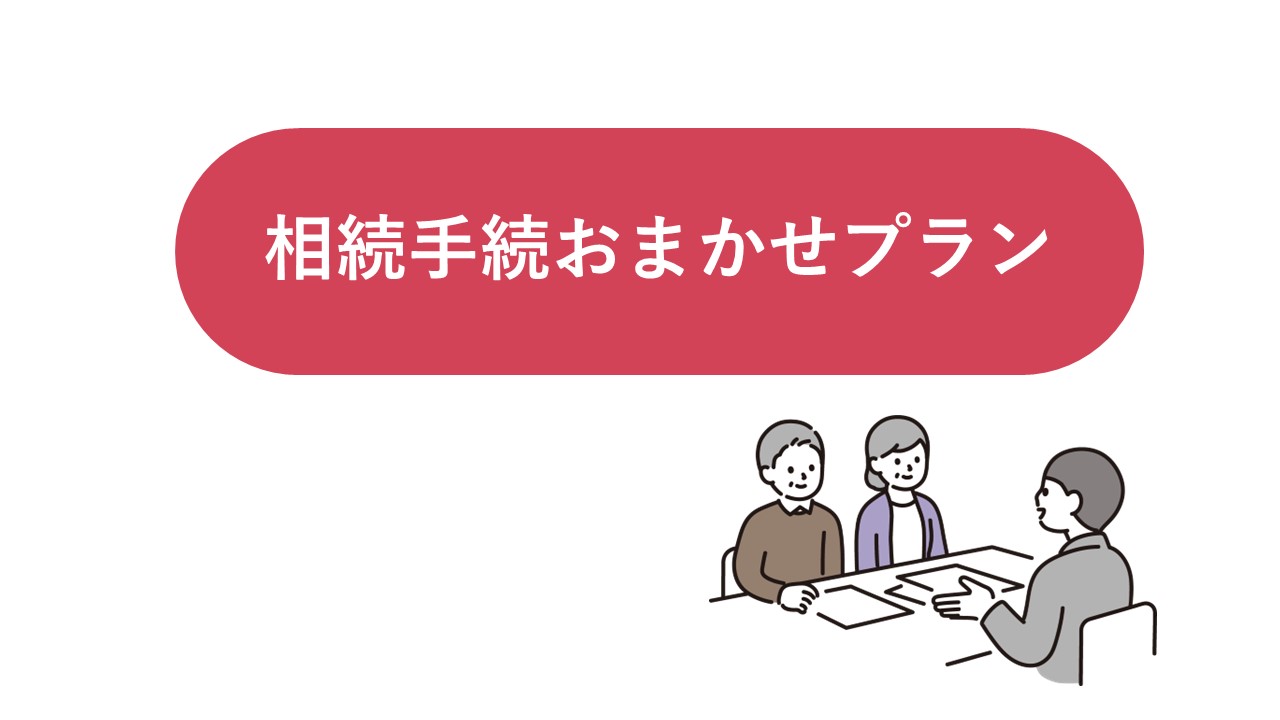こんにちは。 リーガル・フェイスです。
相続が発生すると、亡くなった方の財産を遺族が全て引き継ぎます。
この相続する財産にはプラス財産だけでなく借金などマイナスの財産も含まれることから相続人の生活に大きな影響を与えることになります。
相続財産で多くの人が思い浮かべるのは不動産や預貯金、株式といったものだと思われますが、相続財産はこれらだけでなく、思いもよらないものがあるということもあります。
相続を承認するか相続放棄するかは相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければならないという期限があります。
また、相続税の申告は相続開始から10か月以内に行う必要があります。
思いもよらない財産を見落してしまったままこの期限が過ぎてしまった…
相続放棄をする期間までにその存在を知らなかった…
相続税の申告時に相続財産を漏らしてしまい追徴課税の対象になってしまった…ということもあり得ます。
ここでは、見落としがちな相続財産の主なものについてお話しいたします。
1.見落としがちな相続財産
① デジタル財産
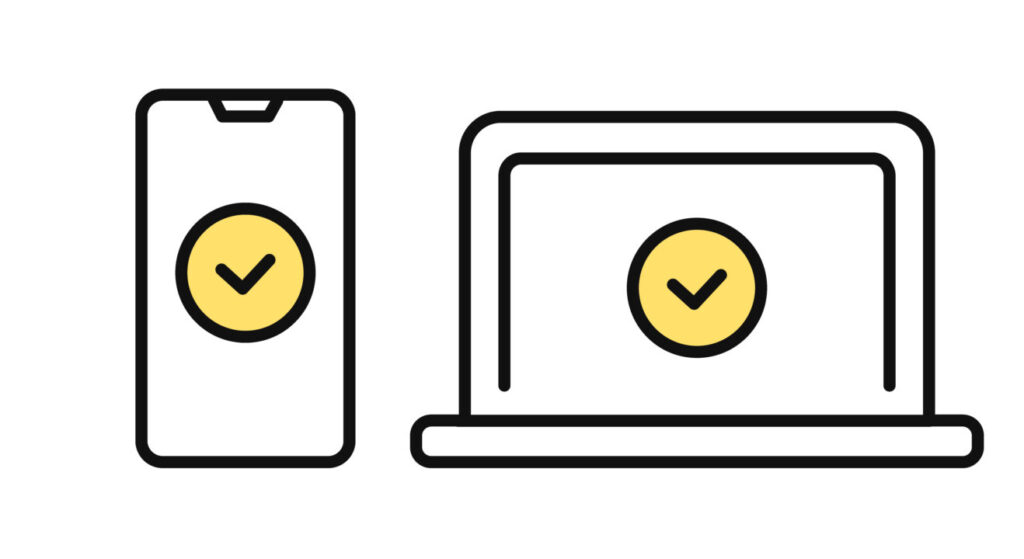
スマートフォン、パソコン、クラウドサービスなど、私たちは多くのデジタルツールと共に生活しています。
これに伴い、相続財産にもデジタル財産が含まれます。
デジタル財産とは、例えば、オンラインバンキング、仮想通貨、電子マネーや、写真・音楽・映画などのデジタルコンテンツがこれに該当します。
特に問題となるのは、仮想通貨や電子マネーなどを管理するデジタルウォレットに関連する財産です。
これらは、書面など物理的な形態がないため、相続人が故人から情報を伝えられていないとその存在自体を知らないということになり相続財産から見落としてしまうことが多くなります。
また、仮想通貨は取引所のアカウントやウォレットの秘密鍵がなければアクセスできないため、個人がその管理方法を何も残していない場合、その財産を取り出すことができずに永遠に失われてしまう可能性もあります。
さらに仮想通貨の存在を見落として相続税申告から漏れてしまうと、税務署に指摘されるリスクがあります。
税務署は調査権限があるため、取引所へ照会して仮想通貨の保有状況を把握しています。
申告漏れが発覚した場合、本来の税額に加えて無申告加算税や延滞税が課され、税金の負担がますます重くなります。
このように相続人がデジタル財産の存在に気づく前に、時効やシステムの制約で取り戻せなくなるケースもあります。
デジタル財産については、生前からの整理・管理・対策(信頼できる人に伝えておくことやエンディングノートへの記載、遺言書の作成等)が非常に重要です。
こちらもご参照ください。
デジタル遺産とは | リーガル・フェイスの士業コラム | 新宿で相続や遺言の無料相談なら司法書士法人リーガル・フェイスへ
② 生命保険の死亡保険金

生命保険は、契約者が亡くなった際に受取人とされた遺族に保険金(死亡保険金)が支払われます。
死亡保険金は高額なことも多く、相続人にとっては重要な財産となりますが、死亡保険金が相続財産となるかどうかについては、注意が必要です。
死亡保険金は、通常、指定された受取人に直接支払われる受取人固有の財産であるため、相続財産には含まれません。
しかし、受取人を被相続人自身とした場合や、受取人が明確に指定されていない場合には、死亡保険金が相続財産の一部となることがあり、遺産分割が必要であるのに見落としてしまう可能性があります。
また、家族が生命保険の契約内容や受取人を知らなかったり、そもそも保険契約の存在に気づかないまま相続が進んでしまうこともあり得ます。
こうした場合、後になってから保険金の存在が明らかになり、相続人間での争いが発生することも考えられます。
保険金の受け取りに関する情報をきちんと整理しておくことが重要です。
こちらもご参照ください。
相続財産って何? みなし相続財産にも注意が必要です | リーガル・フェイスの士業コラム | 新宿で相続や遺言の無料相談なら司法書士法人リーガル・フェイスへ
③ 未登記の不動産

不動産は、相続財産の中でも特に大きな額を占めます。
しかし、相続人がそのすべてを把握しているとは限りません。
相続前に故人から相続人に知らされていない場所に存在する不動産、特に未登記の不動産は所有者の確認が難しく相続財産から見落とされる可能性が大きいです。
また、未登記の不動産は、相続手続きが非常に複雑になる可能性があります。
加えて、未登記でかつ相続登記をしないでいると、不動産を売却したいときや不動産を何かに利用したいというときに所有者としての名義がないことから希望をかなえることが難しくなってしまうということもあり得ます。
したがって、相続前にすべての不動産を確認し、所有者が誰か、登記がされているかどうか等の状況をしっかりと整理しておくことも重要になります。
こちらもご参照ください。
未登記建物の相続について | リーガル・フェイスの士業コラム | 新宿で相続や遺言の無料相談なら司法書士法人リーガル・フェイスへ
④ 借金や保証債務

相続には、「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」も含まれます。
多くの人が相続財産として注目するのは、預金や不動産などのプラスの財産ですが、借金や保証債務などのマイナス財産も無視できません。
特に、金融機関からの借入れや、個人が連帯保証人になっている場合、相続人はその義務も引き継ぐことになり、相続人が返済をしていくことになります。
相続人が故人の借金や保証債務を知らない場合、後になって債権者から返済してくれと請求が来ることもあります。
そのときに相続放棄をしようとしても相続放棄が認められない状況になっていることもあり得ます。
そのため相続開始後、速やかに故人の債務内容を調査することが非常に大切です。
そして必要に応じて速やかに相続放棄や限定承認の手続きを行いましょう。
もし、相続放棄をしなければ、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐことになり、相続人にとって大きな負担となってしまいます。
相続の限定承認とは、相続人が相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐ相続の方式です。
⑤ その他の財産

相続財産には、他にもさまざまなものがあります。
たとえば、骨董品や美術品、ゴルフ会員権、さらには著作権・特許権なども価値のある財産です。
これらの財産は、相続人がその価値に気づかずに処分してしまったり、財産とは思わず見落としてしまうことがあります。
また、親が介護施設に入っていた場合、その預かり金や保証金が相続財産として返還されることもありますので、施設との契約内容をよく確認する必要があります。
その他、故人が銀行に貸金庫を借りていた場合、中には現金、宝石、契約書類などの重要な財産が眠っている可能性もあり、これも見落としがちな相続財産の一つとなります。
2.相続財産調査のポイント
相続財産の調査をするには、次のことを確認をすることが効果的です。
(1) 郵便物の確認
銀行、証券、保険などの通知が届いていないか確認。
(2) 通帳・取引履歴の精査
他行への送金、保険料の引き落とし、証券口座への入金などをチェック。
(3) スマホ・パソコン・メールの確認
電子マネーやネット証券、仮想通貨の情報などをチェック。
(4) 未登記不動産の確認
固定資産税の通知書が届いていないか確認。役所で名寄帳を確認。
(5) 保険証券・契約書類の確認
保険の有無と内容、解約返戻金の存在を確認。
(6) 貸金庫の有無の確認
よく使っていた銀行に照会し、利用履歴の有無を確認。
(7)年金・退職金の申請
年金事務所や故人の勤務先に連絡。
(8) 借入金・保証債務の調査
信販会社など債権者からの通知、信用情報開示請求などを行う。
3.まとめ
相続において見落としがちな財産は、非常に多いです。
デジタル財産や生命保険、未登記の不動産、借金や保証債務、さらには骨董品や著作権など、どれも重要な財産であって、これらを見逃すことは後々大きなトラブルを引き起こすことになり得ます。
相続が開始された際には、できるだけ早くすべての財産を調査し、必要な手続きを行うことが重要となります。
また、相続開始前に生前対策を取っておくことも非常に有効であり重要です。
相続財産を把握することが難しいと予想される場合や生前対策を取っておきたい場合などは、できるだけ早めに税理士や弁護士、司法書士などの専門家へ相談することが望ましいでしょう。

四年制大学の法学部在籍時に、友人と一緒に司法書士資格の勉強を始める。大学を卒業した年に見事合格を果たした後、司法書士事務所へ入所し、商業登記を中心に経験を積む。その後、30歳を迎えることを機に一般企業の法務部へ転職。10年ほど司法書士業界を離れていたが、数年前に再び司法書士業界へ。そして幅広い業務経験を積むため、2022年リーガル・フェイスへ入所する。休日は2児の父として趣味の料理を振る舞う。得意料理はグラタン、好きな食べ物はラーメンと焼肉。