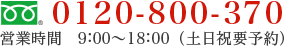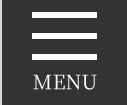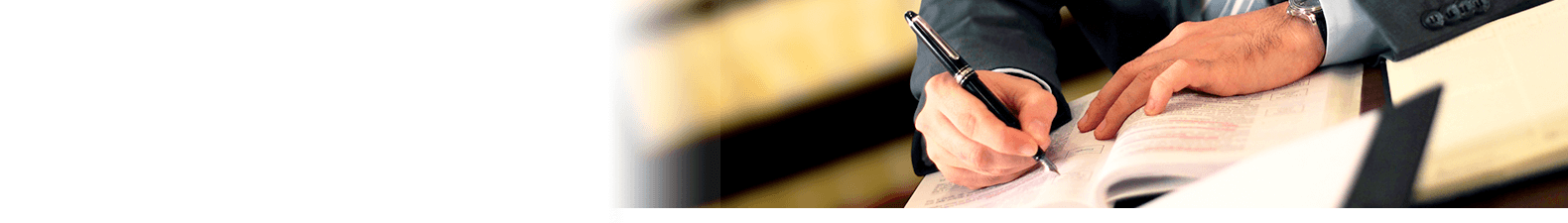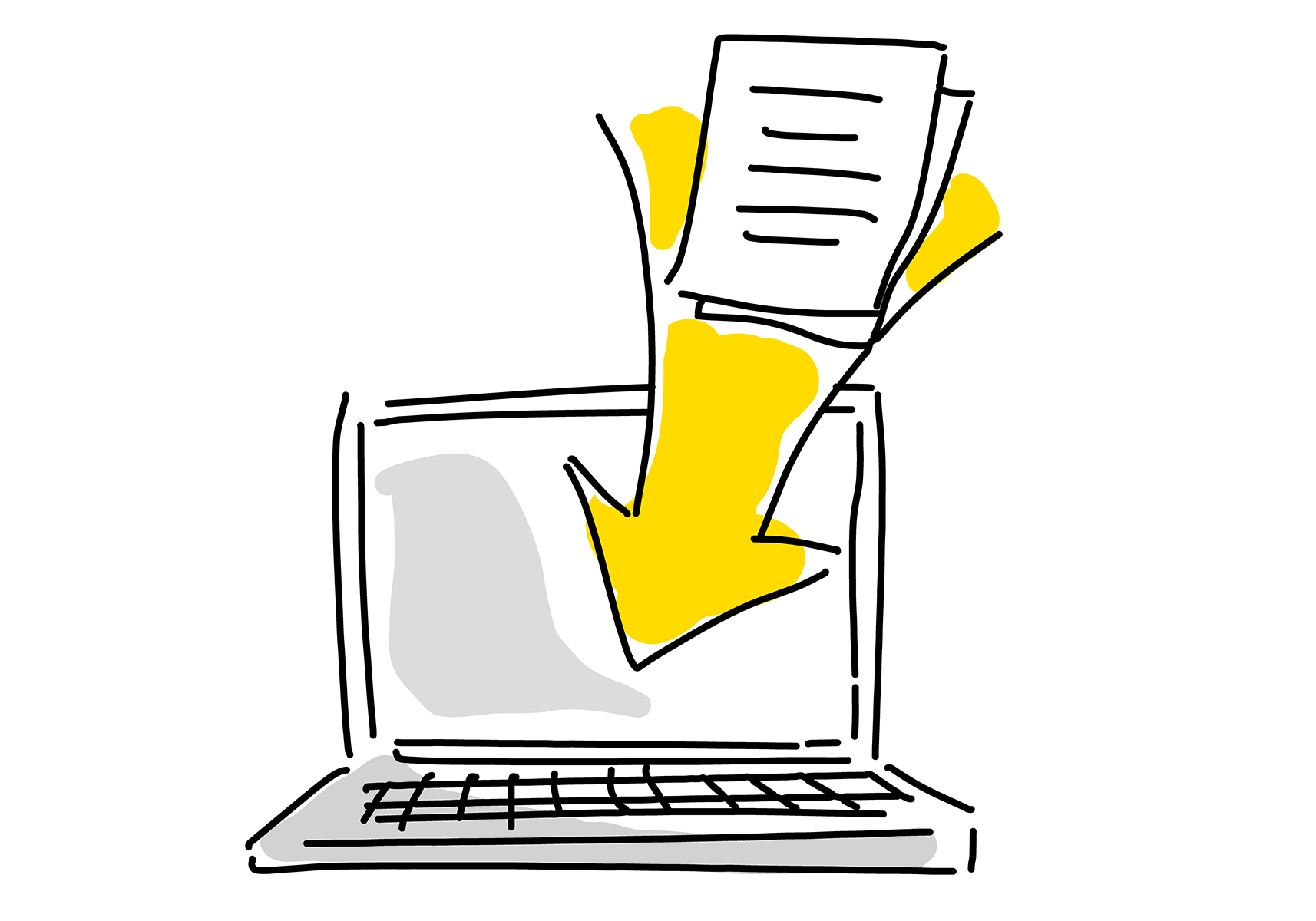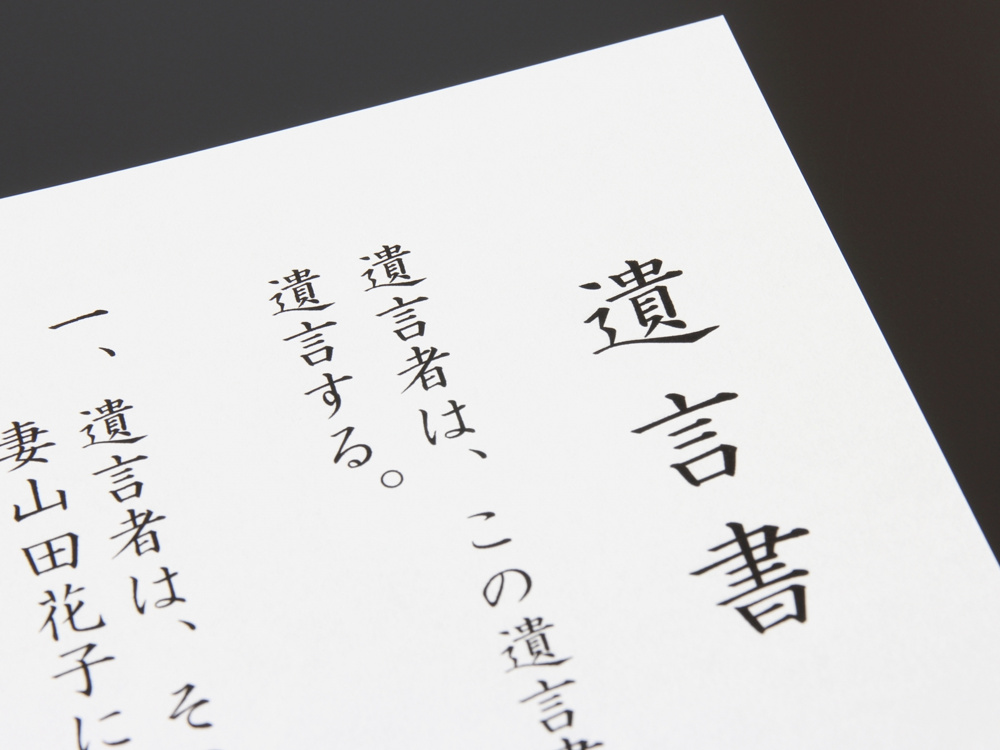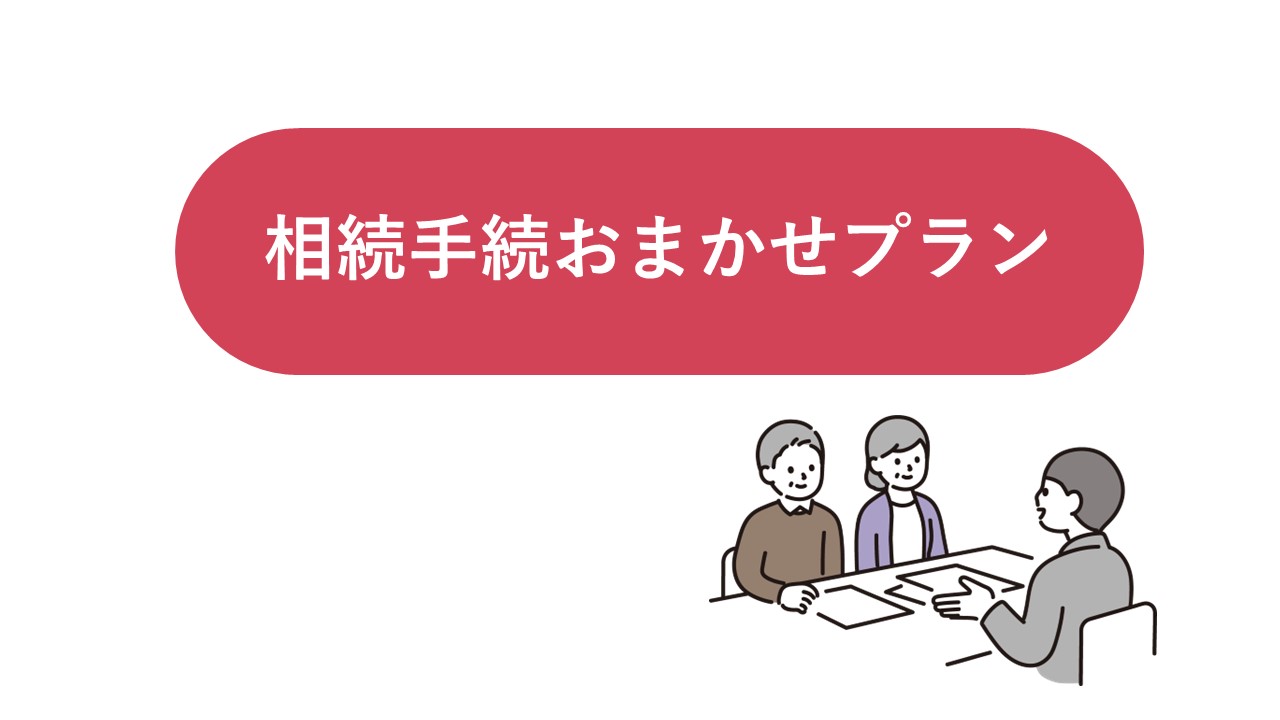こんにちは。
リーガル・フェイスです。
「疎遠の親戚が亡くなった。相続人は自分だけだが、借金があるようなので、相続放棄をしようと思う。」
孤独死が問題となっている現在、上記のように、相続放棄を考える方は、少なからず増えてきているのではないでしょうか。
では、亡くなった方の遺品については誰が整理するのでしょうか?
遺品の整理は、原則として相続人の義務であり、相続放棄をする場合でも、管理義務が生じ、遺品を適切に取り扱う必要があります。
しかし、遺品の整理をすると、相続放棄ができなくなる場合もあり、注意が必要です。
今回は、相続放棄と遺品を整理する際のポイントについてお話しします。
1.相続放棄と遺品の整理について
相続放棄とは、相続が発生した際、相続財産となる資産や負債等の権利や義務を一切引き継がず、放棄することです。
相続の開始を知ってから3か月内に、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申述します。
相続放棄について詳細はこちら→相続放棄はどうやるの? やり方まとめ【四コマつき】
遺品の整理とは、故人が残した品物を整理することです。
遺書や通帳等を確認し、誰が何を相続するかを決めていきます。
遺品を整理することは、故人の死と向き合うことにもなるで、気持ちの整理をつけるために処分を選ぶ場合もありますし、親族だけで処分ができない場合は、業者に整理を頼むこともあります。
2.相続放棄ができなくなる場合~「単純承認」とは~
相続放棄ができなくなる場合として、単純承認した場合が考えられます。
単純承認について、民法では、以下の通り定められています。
民法第921条 (法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
このうち、遺品の整理と関わってくるのは、第1項になります。
冒頭で、遺品の整理をすると、相続放棄ができなくなる可能性がある、と述べましたが、遺品の整理が故人の相続財産の「処分」に当たる場合、相続を認めたことになるので、以後、相続放棄はできなくなる、というわけです。
では、どのような場合が相続財産の「処分」となるのか、詳しく見ていきましょう。
3.相続財産の「処分」
相続財産の「処分」とは、相続財産の現状、性質を変える行為をさしており、法律行為のみならず、事実行為も含みます。
通説や判例では、相続財産の「処分」とは、限定承認又は相続放棄前になされたものに限定される、としています。
【該当例】
①故人の預貯金の引き出し、解約、名義変更
②家屋の解体、売却
③賃貸アパートの解約
※故人が賃貸アパートに住んでいた場合、管理会社やオーナーから部屋の明け渡しを要求されます。
しかし、勝手に解約をすると、故人の賃借権を処分したものとみなされ、相続放棄が認められない可能性があります。
なお、管理会社やオーナーから一方的な解約をされた場合は、後で説明する保存行為(弁済期が到来した債務の履行)に該当するので、「処分」には当たりません。
この場合でも明け渡しの際の遺品の処分については注意が必要です。
④家具や家電などの処分
※家財処分については、無価値であっても、しないでおく方がよいでしょう。
故人が賃貸物件に住んでいた場合は、管理会社やオーナーに事情を説明して、慎重に対応しましょう。
⑤相続財産中の債権についての訴訟提起
※訴訟を起こしたい場合は、利害関係人として、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を求め、選任された相続財産管理人に訴訟を提起してもらいましょう。
⑥相続債務の弁済(税金や借金、入院費等の支払い)
※故人の亡き後に届いた請求書について、相続財産から支払った場合は、相続財産の「処分」となります。
相続人が、自分の財産から支払うのであれば、相続財産の「処分」に該当しないため、相続放棄の障害とはなりません。
⑦遺産分割協議の成立
※遺産分割協議は、故人の全ての財産を把握したうえで、その承継について相続人間でなされるものです。
そのため、遺産分割協議が成立すると、通常は、相続財産の「処分」とみられます。
⑧生前にされた贈与契約に基づく所有権移転登記手続きの履行
このように、上記①から⑧に該当する行為等をした場合、相続放棄は認められなくなってしまいます。
遺品の管理は必要ですが、安易に故人のものに触れたり、持ち出したりしないようにしましょう。
4.「保存行為」
一方で、民法第921条但し書きにおいては、「保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすること」は、「処分」に当たらない、と定めています。
「保存行為」とは、相続財産の現状を維持するのに必要な行為をさしています。
【該当例】
➀故人が住んでいた家の崩れそうなブロック塀の補修
②相続財産中の債権の催告
※債権者に催告をすることは、時効の完成を遅らせる効果をもたらすので、「保存行為」にあたりますが、あくまで回収したお金を相続財産として保管する場合を想定しています。判例の中には、相続人が、自分が受け取ってよいお金だ、と認識をして催告をした結果、「処分」とみなされたものもあります。
また、訴訟を提起する行為は「処分」に当たりますので、気を付けましょう。(上記3.⑤)
5.その他の行為
3.相続財産の「処分」及び4.「保存行為」で相続財産の「処分」と保存行為についてまとめましたが、以下の場合も「処分」とはなりません。
➀形見分け
※故人が所有していたものをもらう場合、それが経済価値を有しないものであれば、相続財産の「処分」にはあたりません(写真や手紙等)。
時計や自動車、貴金属等については、高価なものもありますので、安易に形見分けをしない方がよいでしょう。
②葬儀費用の支出、墓石や仏具の購入
※葬儀を執り行うことは、日本の慣習で認められています。
判例では、常識の範囲内での費用であれば、相続財産から葬儀費用を支払うことは、相続財産の「処分」に該当しないと判断される傾向にあります。
しかし、墓石の購入費用が社会的に不相当に高額である場合は、「処分」とみられる可能性があります。
裁判所では個別判断をしているため、相続財産からの支払いは慎重にすべきでしょう。
また、保険金の受領と消費については、注意が必要です。
保険金を受け取り、使った場合が相続財産の「処分」に該当するかは、保険金が相続財産に含まれるかどうかによって決まり、保険契約の内容によって異なっています。(例:死亡保険金)
受取人が相続人の場合
保険金請求権は相続人の固有財産となり、相続財産に属しません。
従って、相続人が保険金を受領し、使ったとしても、単純承認をしたものとはなりません。
受取人が故人の場合
故人が保険金受取人と指定されており、相続人が保険金を受領した場合、保険金請求権は一度故人に帰属し、相続財産として相続人に承継されたと考えられます。
そのため、相続人が、故人の保険金請求権に基づいて保険金を受領し、それを使った場合は、単純承認したものとみなされる、とした判例もあります。
6.財産調査
相続放棄をしようと考えている場合でも、故人の財産調査をすることは可能です。
民法第915条第2項では、以下の通り定めています。
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
遺品に少しでも手を付けてしまったら相続財産の「処分」となるわけではなく、相続人には、相続財産の状況を把握するために、故人の家の中に入り、通帳や証券関係書類、権利証等を探して、プラス、マイナスの財産を調査することが認められています。
その際、見落としがちな相続財産についても注意しましょう。
詳細はこちら→見落としがちな相続財産
7.まとめ
いかがでしたか?
相続放棄をする前に、慌てて遺品を整理してしまうと、それが相続財産の処分とみなされ、放棄ができなくなってしまうことがあります。
遺品の整理をする場合は、財産調査をして、相続をすることが確定してから着手しましょう。
とはいえ、相続財産について、どのように調査をすればよいかわからない、という方もいらっしゃると思います。
リーガル・フェイスでは、相続財産調査及び放棄手続きのお手伝いもしています。
お困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

長野生まれ東京育ち。大学卒業の年に司法書士資格を取得。他事務所で不動産登記、商業登記を経験。規模が大きい事務所で働きたいと思いリーガル・フェイスへ入所。長く不動産登記部門にいたが、これからは司法書士として相続関係のやりたいと思い相続部門へ異動。好きな食べ物は焼肉、お酒、珈琲、おせんべい