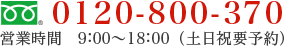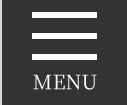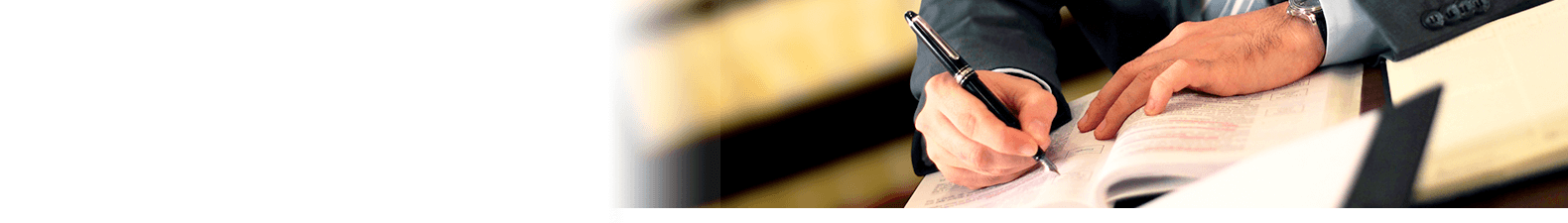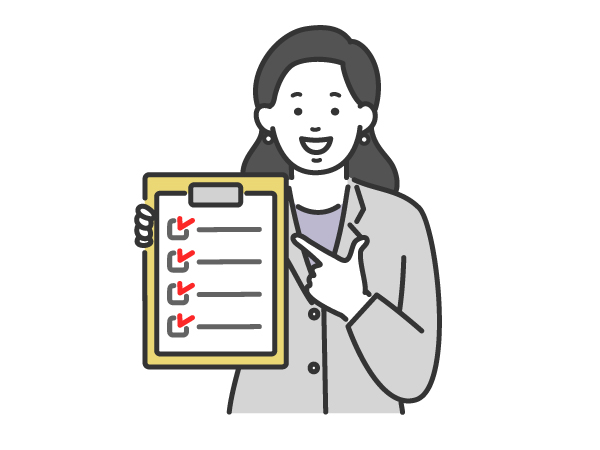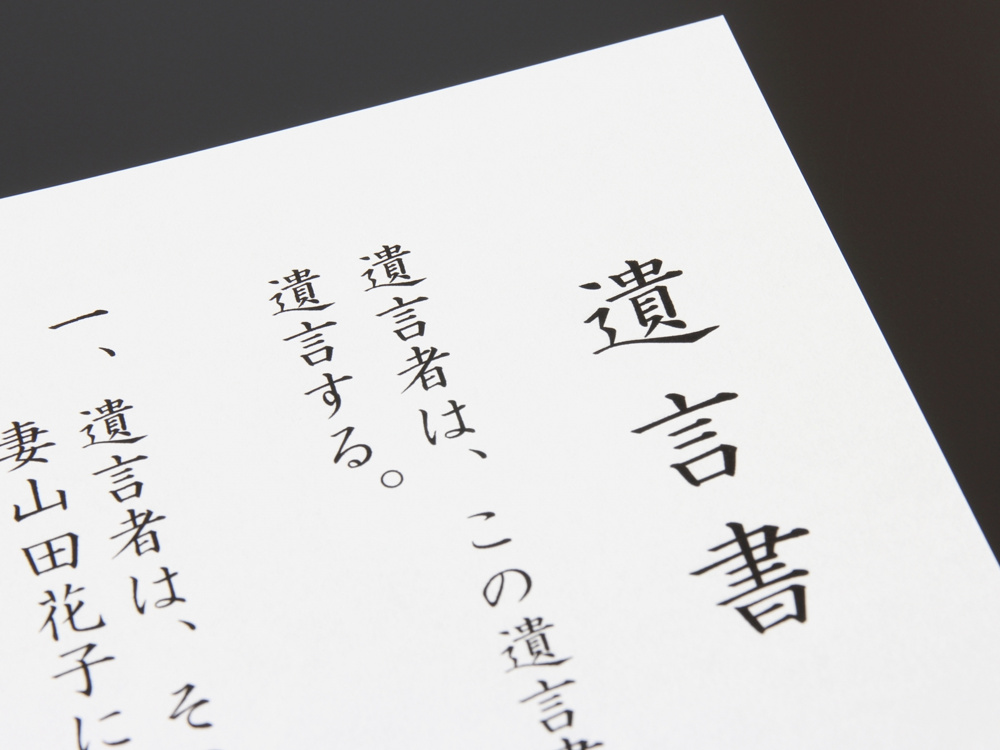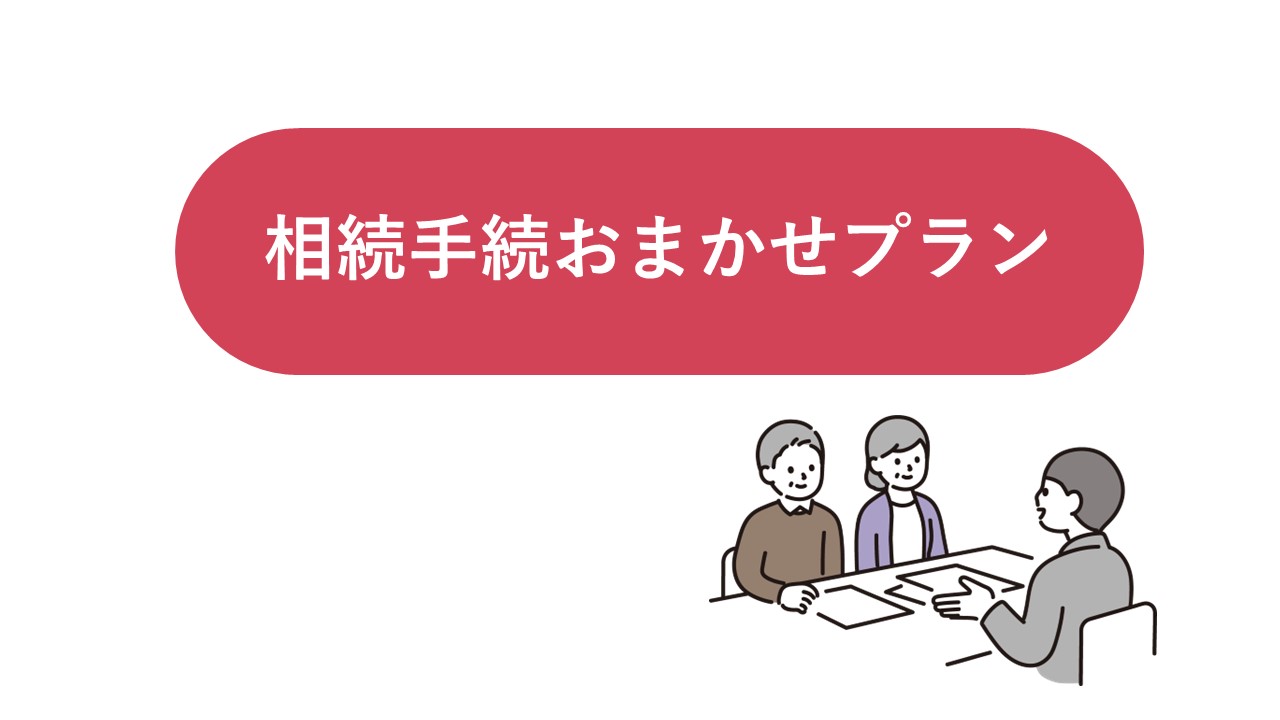はじめに
近年、資産の多様化や海外勤務、移住などにより、日本国内に限らず海外に預金口座を保有する人が増えています。
しかし、相続の際に「海外預金」は国内資産と異なる取り扱いが必要であり、手続きを怠ると重大な問題につながることもあります。
この記事では、海外預金の相続に関する基本知識、手続きの流れ、税務上の注意点、そして円滑に相続を進めるための対策について解説します。
【目次】
1 海外預金を相続する際の法律
海外預金の相続でまず確認すべき点として、国によって相続に関する法律が異なるという事項が挙げられます。
前提として、「誰が相続人になるか」については被相続人(亡くなった方)の本国法が適用できるため、被相続人が日本人の場合は海外預金であっても日本の法律によって相続を進めることができます。
一方で、預金の払戻しなどの具体的な手続きについては、現地の法律や制度に従って行う必要があることに注意が必要です。
海外の相続に関する法律は、大まかに「英米法系」と「大陸法系」の2つに大別されます。
英米法では、不動産については不動産の所在地の法律を、それ以外の動産(預貯金等)については被相続人の本国法を適用するとされています。(相続分割主義)
一方で大陸法では、預金や不動産などすべての相続財産について被相続人の本国法を適用するとされています。(相続統一主義)
では、次から英米法と大陸法それぞれの相続手続きの流れについて確認してみましょう。
2 英米法の相続手続き
英米法系の国では、相続が開始すると、原則として「プロベート」と呼ばれる手続きを経て相続財産の確定と分配が行われます。
※英米法系の国
イギリス・アメリカ・カナダ・オーストラリア・香港・シンガポール・マレーシアなど
2-1プロベートとは
プロベート(Probate)とは日本にはない相続の制度で、相続人が遺産を相続するためにしなければいけない裁判所の手続きを言います。
プロベートの手続きは以下の通りです。
① 裁判所が代表者(遺産管理人)を任命し、海外預金は遺産管理人の管理下に置かれる
② 遺産管理人は裁判所の監督の下、遺言書の有効性のチェックや、相続財産と相続人が誰で あるかの調査を行なう
③ 債務や諸費用を支払い、清算後の相続財産について税務申告・納税を行なう
④ 残余財産について、裁判所から分配の許可を得る
⑤ 預金の払戻し(相続人への分配)を行なう
プロベートの手続き中は相続財産の利用処分が制限され、その費用も高額に上る場合があります。
また、最終的な払戻しが完了するまである程度の期間を要します。
2-2 遺言について
遺言がある場合には、遺言書を裁判所に提出し、遺言の有効性が確認された上で、遺言に従って分配が為されます。
遺言が無い場合は、現地の法律に則って分配が為されます。
2-3 プロベートの手続きが不要な場合
●共同保有財産(ジョイント口座)
共同保有・共同名義となっている財産については、共同保有者がプロベートの手続きを踏まずにその財産を承継できる場合があります。
その一例として、ジョイント口座と呼ばれる共同名義預金が該当します。
●受取人指定のある口座
死亡時の払戻私事条項(受取人指定)のある口座については、プロベートの手続きを経ずに指定した受取人に承継させることができます。
●少額の預金
相続財産総額が少額の場合、資産の種類・金額等を記載し公証した宣誓供述書を準備することにより、プロベートの手続きを経ずに承継できる場合がります。
国や金額により取り扱いも異なるようです。
3 大陸法の相続手続き
大陸法系の国では、上記のプロベートの適用がありません。
※大陸法系の国
フランス・ドイツ・中国・韓国など
① 口座のある現地の金融機関への連絡
(口座名義人の死亡の申出、残高証明の発行やその後の相続手続きに必要な事項の問い合わせ)
② 金融機関ごとの指定に沿った必要書類の収集
(一般的には、口座名義人が死亡した事実を証明する書類、相続人であることを証明する書類、預金払戻し用の申請書など)
③ 必要書類の翻訳
④ 公証役場で書類の認証を受ける
⑤ ④の書類について、外務省の証明を受ける
⑥ ⑤の書類について、口座のある国の駐日大使館で証明を受ける
⑦ 預金の払戻し(相続人への分配)を行なう
※提出先や書類、用途によっては認証・証明の要否が異なります
4 相続手続きを放置した場合のリスク
① 税務調査による追徴課税
海外預金の申告漏れがあった場合、税務調査で発覚すれば、追徴課税・延滞税・加算税などの対象になる事があります。
意図的な隠ぺいと見なされた場合は重加算税が課される可能性もあります。
近年は「CRS(共通報告基準)」の導入により、各国間で金融口座情報の自動交換が進んでおり、海外口座の秘匿は困難になっています。
日本もこれに加盟しており、税務当局が海外預金の情報を把握することは十分に可能です。
② 預金の凍結・強制解約の可能性
手続きを怠ると、海外預金はそのまま口座凍結され、長期間動かせない状態が生じる場合があります。
一定期間を過ぎると、金融機関の規約により口座閉鎖となるリスクもあります。
5 手続きの煩雑さを軽減させるための対策
日本国内と比べ、海外預金の相続手続きは英米法・大陸法のどちらも大変そうだと思われた方もおおいのではないでしょうか。
実際、言語が違うだけでなく相当の手間と時間がかかり、場合によっては弁護士等の専門家に手続きを依頼することで更なる費用負担も考慮しなければなりません。
相続人の負担を減らすため、生前の元気なうちに下記のような対策を検討するのも一案です。
① 生前の情報共有
相続人に対して、生前から「どこに、どれだけの資産があるのか」を伝えておくことが非常に重要です。口座番号、金融機関名、支店、通貨などの情報を整理しておくと、相続手続きが円滑に進みます。
② 遺言の作成
海外資産がある場合は、現地の法律に基づいた、その国にある財産に限定した現地の言語での遺言書を用意し、公的な効力をもたせておくことも有効です。英米法系の国であっても、プロベートの手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
③ ジョイント口座や受取人指定口座を利用する(2-3参照)
6 さいごに
さて、いかがでしたでしょうか。
海外預金の相続は、国内の相続に比べて手続きや税務処理が複雑です。
放置や申告漏れは、法的・経済的なリスクを伴います。しかし、事前の情報整理と適切な手続きを踏むことで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。
グローバル化の進展に伴い、海外預金の保有率は今後も増加していくことが見込まれます。
海外に財産を持つことおメリットと相続時の手続き等におけるデメリットはしっかり考慮しておき、将来家族が安心して手続きできるよう準備を始めておくことが肝要ですね。

大学(法学部)を卒業後、リーガル・フェイスへ入所。そこから14年間、補助者として不動産売買に伴う登記をメインとして業務に邁進し、2021年より相続・商業課へ異動。ただ「こなす」のではなく、自分だけの「付加価値」を付けながら一人ひとりのお客様へ最善のサービスを提供できるよう、新たな環境で日々勉強中。趣味はランニング、好きな食べ物は唐揚げと夏野菜(ナス、トマト、オクラなど)。