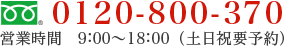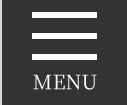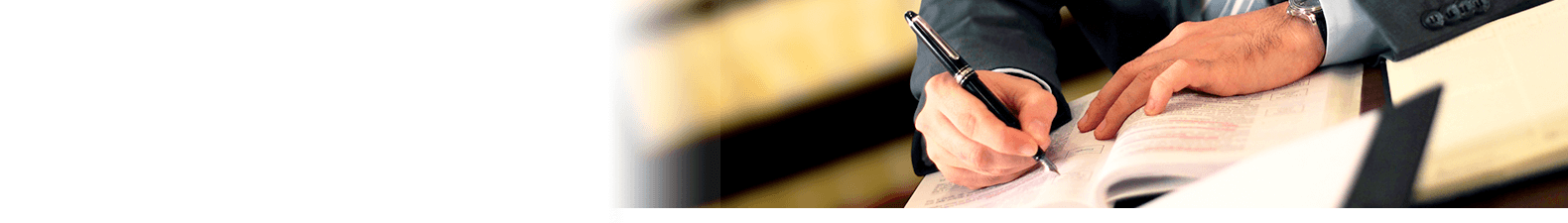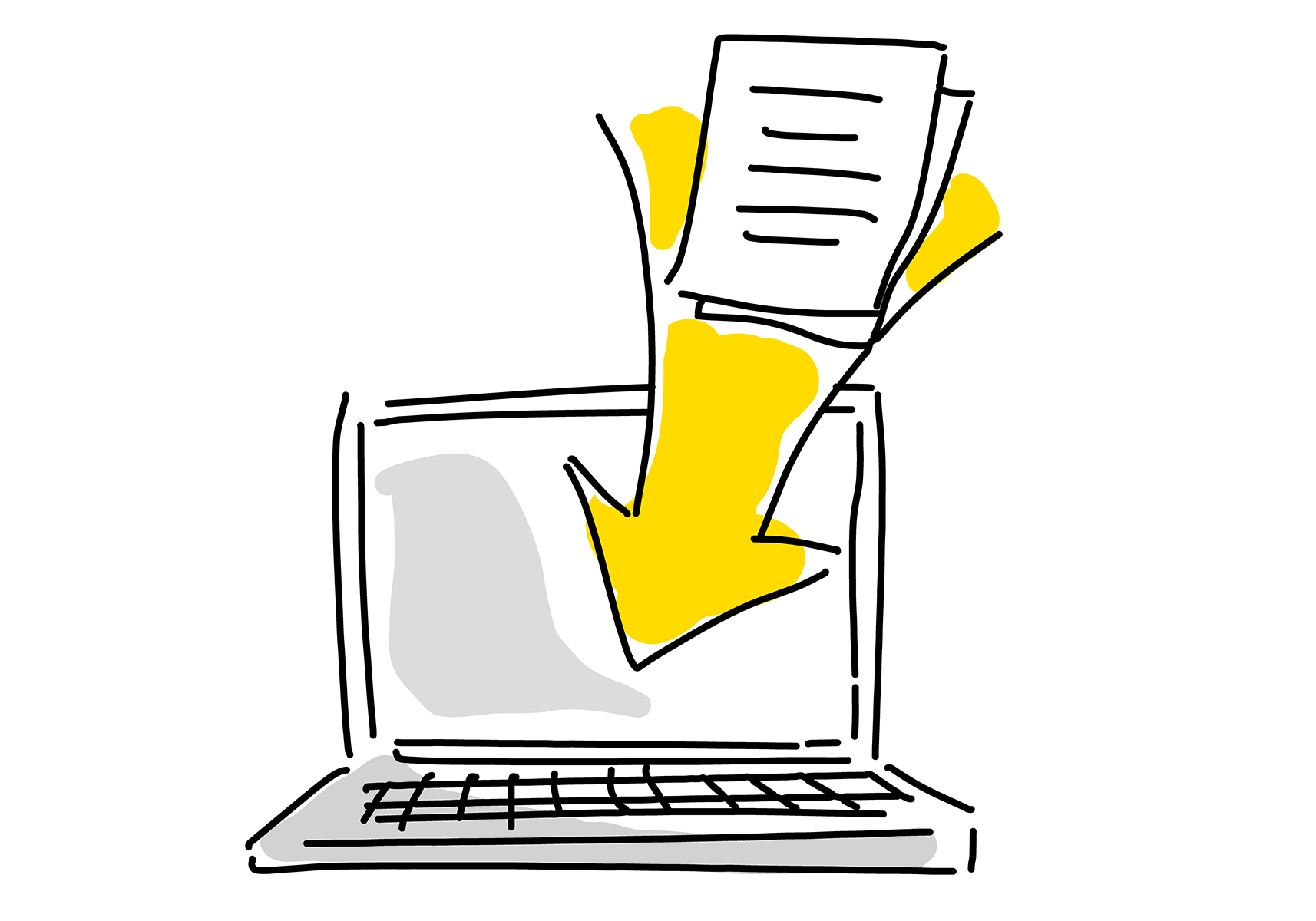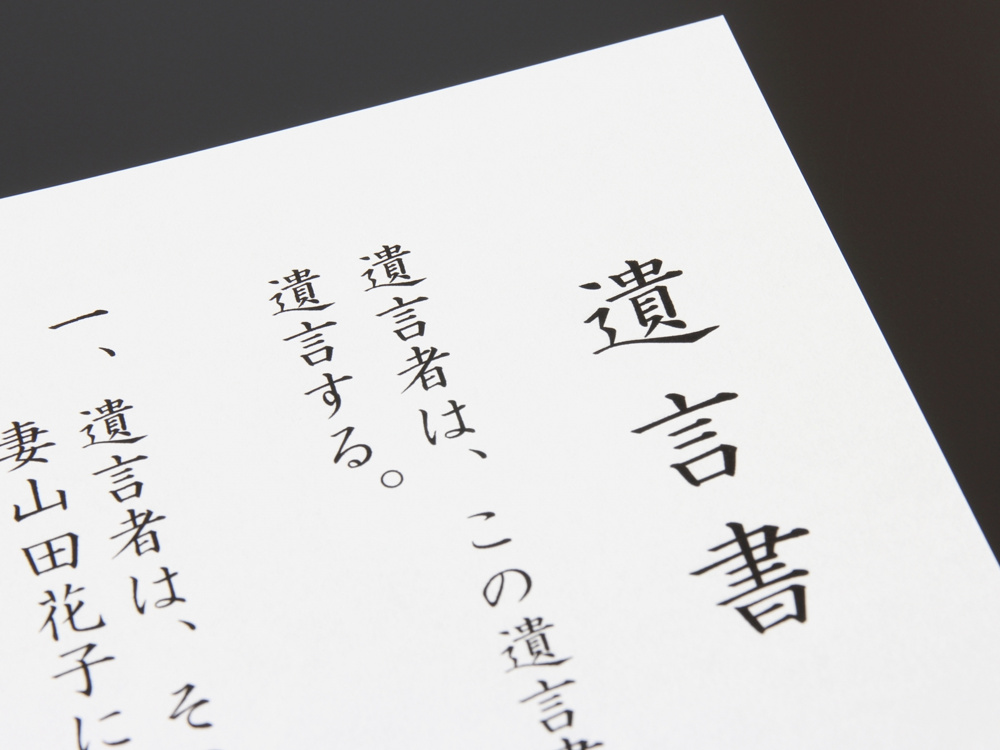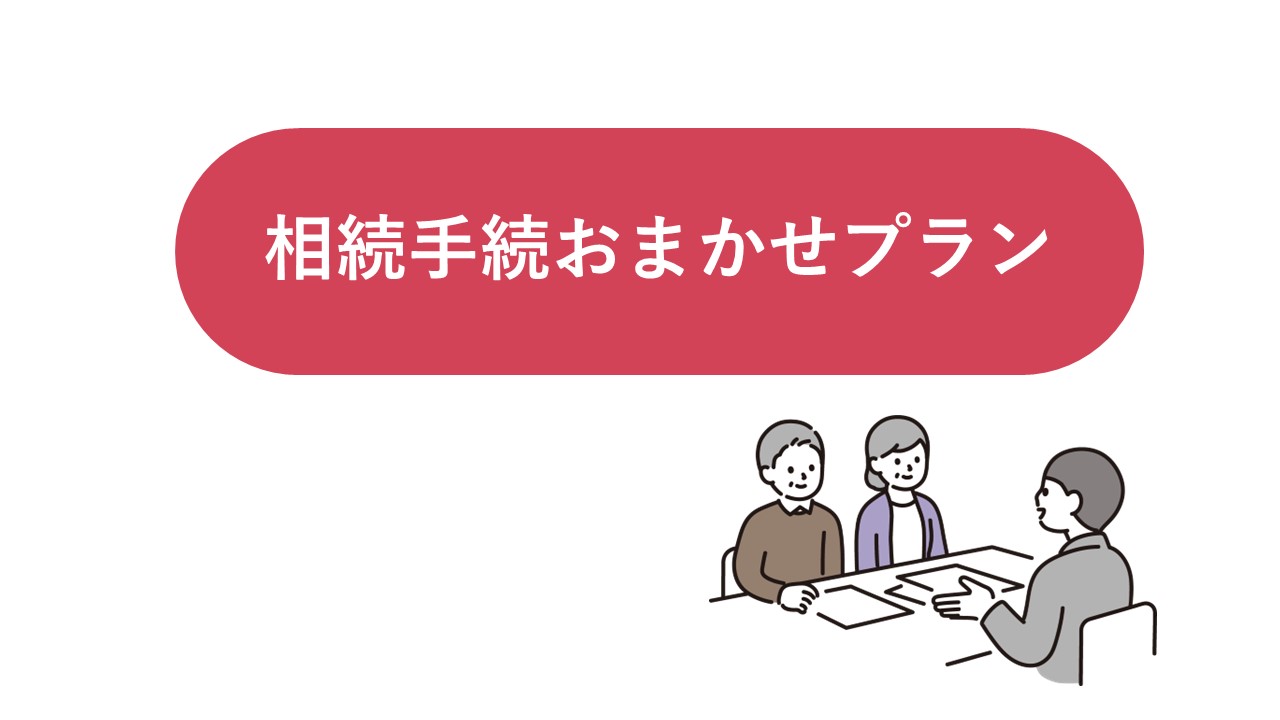こんにちは。
リーガル・フェイスです。
離婚は人生の大きな転換点となるものであり、精神的・肉体的な負担に加え、財産分与、不動産の名義変更、養育費、年金分割といった複雑な法的手続きが伴います。
特に、不動産や住宅ローンを抱えるご夫婦の場合は名義変更や銀行との手続には慎重な対応が求められます。
本コラムでは、司法書士の視点から、財産分与、登記手続き、住宅ローン、年金分割を中心に、実務的なポイントをご紹介します。
【目次】
1.財産分与とは
財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚時に公平に分ける制度です。
財産分与の性質には下記3つがあると解されており、特に①が基本であると考えられています。
①夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配
②離婚後の生活保障
③離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質
なお、財産分与は民法第768条に規定されており、協議離婚では夫婦の合意で分与内容を決めます。
合意に至らない場合は、離婚後2年以内に家庭裁判所へ請求できます(令和6年5月成立の民法改正により、請求期間が「5年以内」と改正されることになっています)。
2.未成年の子供がいる場合の手続き
離婚時に未成年の子供がいる場合には、財産分与以外に以下の手続きが必要です。
親権の決定
未成年の子がいる夫婦が離婚した場合、まずは夫婦の協議によって親権者を決めることになります。
協議が整わない場合は、裁判所が決めることになります。
その判断においては、実務上、従前の子の監護実績、現在の監護状況、子供の意思が重視されているようです。
養育費の取り決め
養育費は「子の監護に必要な費用」として、非監護親から監護親に支払われる未成熟の子の養育に要する費用を言います。
面会交流
親権を持たない親と子の交流を確保します。
取り決めは、口約束ではなく書面で残すことが重要です。
3.財産分与の種類と役割
財産分与には以下の種類があります。
清算的財産分与
婚姻中に形成した夫婦共有財産(不動産、預貯金、退職金など)を清算します。
原則として2分の1ずつ分与されますが、貢献度や生活状況により調整可能です。
扶養的財産分与
離婚後に経済的に困窮する配偶者の生活を支えます。
慰謝料的財産分与
不貞行為や暴力など有責配偶者の行為に対する補償として上乗せします。
4.財産分与の対象と対象外財産
対象
婚姻中に夫婦の協力によって築いた財産(不動産、預貯金、有価証券、自動車、保険
解約返戻金等)。
対象外
婚姻前から有する財産や婚姻中に相続により取得した財産など名実ともに夫婦一方の所有とされる財産は原則として財産分与の対象にはなりません。
なお、退職金については、離婚時にすでに支給されていた退職金は財産分与の対象となりますが、離婚時にはまだ支給されておらず具体化されていない退職金については、裁判例も分かれていますので注意が必要でしょう。
5.債務の法的扱い
夫婦の共同生活によって生じた債務は離婚時に清算の対象として考慮するのが一般的です。
対象債務
住宅ローンや生活費不足のために借り入れた借金、教育ローン 等
※実務上、住宅ローンの債務負担は金融機関との調整が不可欠であり、夫婦間のみでの取り決めによって債権者を拘束することはできません。
対象外債務
ギャンブルや個人的趣味の借金は債務者単独負担です。
6.住宅ローンが残る場合の対応
住宅ローンが残る不動産の分与は金融機関との調整が必須であり、通常は以下の手続を行うことになるでしょう。
売却清算
不動産を売却し、ローンを完済後、残金を分与します。
売却額がローン残高未満の場合、不足分を現金で補填します(例:ローン残高2000万円、売却額1800万円で不足200万円を折半等)。
単独名義への変更
取得者がローンの債務者となる変更をします。金融機関の審査が必須です。
たとえば、妻が自宅に居住継続する場合、夫名義のローンを妻名義に変更します。
※ローン契約は金融機関との合意に基づきます。名義変更には承諾が必要で、審査に通らない場合、売却が現実的です。
7.不動産の所有権移転登記
財産分与で不動産を取得する場合、所有権移転登記が必要です。
これは登記簿上の名義を変更する手続きで、司法書士が代行できます。
協議離婚に伴う財産分与による所有権移転登記の必要書類は、次のとおりです。
【必要書類】
◆離婚についての記載のある戸籍謄本
◆財産分与する対象不動産の権利証(登記済証または登記識別情報)
◆渡す側の方の印鑑証明書(登記申請時点で発行から3ヶ月以内のもの)
◆もらう側の方の住民票(期間制限はありません)
◆対象不動産の固定資産評価証明書(本年度のもの)
◆登記委任状
◆登記原因証明情報
登記原因証明情報は、財産分与協議書などが該当します。
なお、司法書士が登記申請を代行する際には、必要な情報のみをコンパクトにまとめた「登記原因証明情報」というタイトルの書面を司法書士が作成し、こちらを提出することが一般的です。
注意点
通常、離婚に伴う財産分与による所有権移転登記をする場合、登記簿上の名義人の方(渡す側の方)の住所や氏名が変更になっている場合が多いかと思います。
そのような場合には、財産分与による所有権移転登記に先立って、登記名義人の住所・氏名の変更登記が必要になりますので以下の書類も必要となります。
【必要書類】
◆住所変更の経緯が分かる住民票の写しまたは戸籍の附票
◆氏名変更の経緯が分かる戸籍謄本
8.子の氏と戸籍の変更
親権者が旧姓に戻しても、子の氏は自動的に変更されません。
例えば、母親(婚姻時に夫の姓なっていた場合)が親権者となった場合、子供は父親と同じ姓のままとなります。
子供を母親と同一の氏にするには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を提出します。
親と子の戸籍謄本、申立書等の書類が必要となります。
家庭裁判所から許可を取得した後、戸籍の入籍届を提出することで姓の変更が正式に効力を持ちます。
9.年金分割の制度と手続き
年金分割は、離婚した場合に、夫婦二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金や共済年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
具体的には、離婚時の年金分割が行われると、婚姻期間中について、厚生年金や共済年金支給額の計算の基となる報酬額(標準報酬)の記録が分割されることになり、年金額を二人で分割できます。
※年金分割は厚生年金や共済年金を対象としており、基礎年金部分である国民年金は分割の対象外です。
分割方法
合意分割
夫婦の合意で年金を分割する方法。
分割の割合は夫婦の合意、または、裁判手続によって決まった割合となります。
3号分割
サラリーマンの妻である専業主婦の方など、国民年金第3号保険者であった方からの請求により、年金を分割する方法です。
合意分割の請求期限は離婚後2年以内
合意分割手続きの流れ
① 年金事務所で情報通知書を取得し、納付記録を確認します。
② 分割割合を協議し、書類を年金事務所に提出します。
③ 分割決定後、将来の年金に反映されます(即時給付なし)。
※年金事務所が受け付ける合意の方法が限定されていますので、以下の方法等で合意することが必要です
(年金事務所に確認の上手続きを進めることが肝要です)。
・裁判所の調停・審判
・公証役場での公正証書作成
・合意書を夫婦2人(またはそれぞれの代理人)が年金事務所に直接持参 等
10.税務の検討
財産分与として不動産の名義を変更した場合に、贈与税がかかることは原則としてはありませんし、不動産取得税についても、共有財産の清算的な財産分与であれば課税はされないでしょう。
ただし、財産分与をした側には譲渡所得の課税が行われることになります。
財産分与に関しての税務については、税の専門家である税理士に事前によく確認をしておくことが必要でしょう。
11.まとめ
離婚時の財産分与、登記、住宅ローン、年金分割は、離婚後の将来の生活基盤を整える重要な手続きです。
公正証書で合意を明確化しておくことが、将来の安心及び各手続きの簡略化となることもあります。
司法書士、弁護士、税理士の支援で法務・税務リスクを検討しながら進めることが大切です。

千葉県勝浦市生まれ、東京育ち。平成17年に司法書士試験合格。不動産会社・金融関係の企業勤務を経て、相続関連の業務に携わりたいという想いから司法書士法人リーガル・フェイスに入社。主な資格は司法書士、宅地建物取引主任者、貸金業務取扱主任者。趣味は自宅で行うヨガ。好きな食べ物はリーフパイ、お好み焼き、酢めし、磯辺焼きなど。